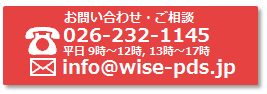2025/04/17 東京コンガラショック・1/行き場失った大量のコンガラ、旺盛な再開発・処理費も上昇
【建設工業新聞 04月 17日 1面記事掲載】
東京都内の解体現場から出た大量のコンクリートガラ(コンガラ)が行き場を失っている。首都圏の旺盛な再開発を背景に発生量は右肩上がり。一方、主な再利用先である路盤の工事量は横ばいで推移しているため、リサイクルの需給バランスが崩れている。余ったコンガラの処理で建設会社や中間処理を担う道路舗装各社は対応に苦慮している。建設廃棄物の資源循環をどう成立させていくのか現状を追った。
「ここ2年ほどは処理依頼をお断りすることもある」。建設プロジェクトが旺盛な都心に近く、廃材処理のニーズに対応してきた道路舗装会社が運営する都内の合材工場。その工場長は近年の処理ニーズの高まりに対し複雑な思いを吐露する。同工場に寄せられるコンガラの処理依頼は年々増加しており、2022年ごろから需給バランスが崩れてきたという。それ以前は東京五輪に関連した道路工事などもあり、現場にコンガラ由来の再生砕石を路盤材として供給するなど再利用先が確保できていた。
こうした路盤材を活用する公共工事が減少してきた22年ごろから、コロナ禍で中断されていた大型プロジェクトが再始動し始めた。解体工事が増え「コンガラの供給が需要を上回ってきた」(工場長)。路盤材として供給する現場が確保できないため、直近1年は処理を依頼される量のうち、2~3割程度を断らざるを得ないという。
都内の合材工場のコンガラ受け入れ量は年々増加傾向にある。日本アスファルト合材協会(日合協、今泉保彦会長)が会員企業の合材出荷量を基に算出した推計によると、都内の合材工場で製造したコンガラ由来の再生路盤材の出荷量は21年度258万トン、22年度290万トン、23年度311万トン、24年度(速報値)292万トン。このうち都内で使われず、都外に搬出した量は21年度1万トン、22年度8万トン、23年度13万トン、24年度19万トンと伸びている。受け入れ量に占める都外搬出分の割合も年々上昇傾向にある。24年度はコンガラ受け入れ量が減少しており、日合協は「都内で過度に増加していることから、各工場による受け入れ制限の動きが強まったのでは」とみている。
受け入れ量をある程度抑制しても全てを再生材として都内で消費するのは難しい。複数の工場が東京から離れた関東や東北、北海道といった需要のある地方に輸送して余剰分を処理しているのが実情。東京から離れるほど需要は膨らむが輸送コストも高く付く。
物価高騰のあおりを受け輸送費を含む処理コストが上昇している。コンガラの受け入れ料金を1トン当たり60%引き上げた工場もある。それでもゼネコンや解体業者からの処理依頼は引きも切らない。同様の動きは他の合材工場でも起きており、道路舗装会社の製品販売担当者は「ゼネコン側も工期を厳守するため、処分先の確保に必死だ」とクライアントの事情をおもんぱかる。
多くの合材工場は受け入れ料金を引き上げ遠方への輸送処理コストを吸収し、健全な経営を維持しようと努めている。日合協によると一部の合材工場では、アスファルト合材の供給先である元請(施工会社)からの要請を断れず、赤字を覚悟の上で価格を抑えたままコンガラ処理を引き受けている実態があるという。日合協は「(道路工事の)下請に当たる工場側は、取引継続のため不利な条件でも受け入れざるを得ないのでは」と推察する。
「合材工場がコンガラの処分のため、高額な費用負担を強いられる深刻な状況が続いている」とも指摘。行政などに対して「持続的な資源循環を目指すためには、輸送費の助成といった支援制度を検討してもらいたい。早急に対応しないと業界が疲弊してしまう」と訴える。
「ここ2年ほどは処理依頼をお断りすることもある」。建設プロジェクトが旺盛な都心に近く、廃材処理のニーズに対応してきた道路舗装会社が運営する都内の合材工場。その工場長は近年の処理ニーズの高まりに対し複雑な思いを吐露する。同工場に寄せられるコンガラの処理依頼は年々増加しており、2022年ごろから需給バランスが崩れてきたという。それ以前は東京五輪に関連した道路工事などもあり、現場にコンガラ由来の再生砕石を路盤材として供給するなど再利用先が確保できていた。
こうした路盤材を活用する公共工事が減少してきた22年ごろから、コロナ禍で中断されていた大型プロジェクトが再始動し始めた。解体工事が増え「コンガラの供給が需要を上回ってきた」(工場長)。路盤材として供給する現場が確保できないため、直近1年は処理を依頼される量のうち、2~3割程度を断らざるを得ないという。
都内の合材工場のコンガラ受け入れ量は年々増加傾向にある。日本アスファルト合材協会(日合協、今泉保彦会長)が会員企業の合材出荷量を基に算出した推計によると、都内の合材工場で製造したコンガラ由来の再生路盤材の出荷量は21年度258万トン、22年度290万トン、23年度311万トン、24年度(速報値)292万トン。このうち都内で使われず、都外に搬出した量は21年度1万トン、22年度8万トン、23年度13万トン、24年度19万トンと伸びている。受け入れ量に占める都外搬出分の割合も年々上昇傾向にある。24年度はコンガラ受け入れ量が減少しており、日合協は「都内で過度に増加していることから、各工場による受け入れ制限の動きが強まったのでは」とみている。
受け入れ量をある程度抑制しても全てを再生材として都内で消費するのは難しい。複数の工場が東京から離れた関東や東北、北海道といった需要のある地方に輸送して余剰分を処理しているのが実情。東京から離れるほど需要は膨らむが輸送コストも高く付く。
物価高騰のあおりを受け輸送費を含む処理コストが上昇している。コンガラの受け入れ料金を1トン当たり60%引き上げた工場もある。それでもゼネコンや解体業者からの処理依頼は引きも切らない。同様の動きは他の合材工場でも起きており、道路舗装会社の製品販売担当者は「ゼネコン側も工期を厳守するため、処分先の確保に必死だ」とクライアントの事情をおもんぱかる。
多くの合材工場は受け入れ料金を引き上げ遠方への輸送処理コストを吸収し、健全な経営を維持しようと努めている。日合協によると一部の合材工場では、アスファルト合材の供給先である元請(施工会社)からの要請を断れず、赤字を覚悟の上で価格を抑えたままコンガラ処理を引き受けている実態があるという。日合協は「(道路工事の)下請に当たる工場側は、取引継続のため不利な条件でも受け入れざるを得ないのでは」と推察する。
「合材工場がコンガラの処分のため、高額な費用負担を強いられる深刻な状況が続いている」とも指摘。行政などに対して「持続的な資源循環を目指すためには、輸送費の助成といった支援制度を検討してもらいたい。早急に対応しないと業界が疲弊してしまう」と訴える。
日刊建設工業新聞の購読申し込みは、こちら